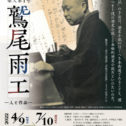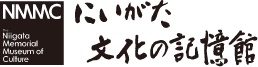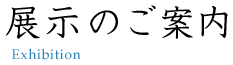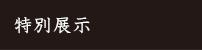2025/04/01~2025/07/06
2025(令和7)年度│岩田正巳 ―日本画の新境地を開く―
三条市に生まれた日本画家・岩田正巳(1893~1988年)は歴史物語などを題材とする大和絵に、現代の息吹を取り入れて、日本画の新境地を開きました。
旧制三条中学校から東京美術学校へ進み、卒業後は、大和絵の流れを汲む日本画家 松岡映丘に師事しました。有職故実に詳しく、映丘と共に「新興大和絵会」、「国画院」を立ち上げて、新しい歴史画の理想を追求しました。戦後は中国、インドへとイメージを広げて、石仏などのシリーズを制作。モチーフも現代風の花鳥、風景、人物などを描き、気品の感じられる画風を確立しました。
本展では、三条市名誉市民第1号に推挙された岩田正巳の画業を、小品を中心に紹介します。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
監 修:横山秀樹氏(美術評論家、元新潟市新津美術館長)
展示協力:新潟市新津美術館、三条市、三条市歴史民俗産業資料館、新潟日報社

2025/07/29~2025/11/03
2025(令和7)年度│戦後80年 捕虜になった記者・小柳胖
新潟日報社の第四代社長・小柳胖(おやなぎ・ゆたか、1911~86年、新潟市生まれ)は太平洋戦争を機に数奇な人生を送った新聞人です。
戦時中、小柳は編集局長として戦争推進に協力する新聞を制作していましたが、昭和19年2月に召集され戦地へ赴きました。太平洋戦争末期に硫黄島で米軍の捕虜となりハワイの捕虜収容所に移されました。そこで小柳は、所長オーテス・ケーリの下で捕虜仲間の記者等とともに対日宣伝ビラを作ることになりました。その目的は戦争の早期終結でした。
終戦の翌年に復員した小柳は新潟日報に戻ると、捕虜体験を語ることなく、経営者として自社や業界の発展に尽力しました。地域振興にも貢献し、晩年は會津八一記念館の設立運動の中心となり、初代館長を務めました。
戦後80年の今夏、“捕虜になった記者”小柳胖の旧蔵資料から、戦争とメディアについて考えてみたいと思います。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
展示協力:新潟日報社、日本新聞博物館、BSN新潟放送
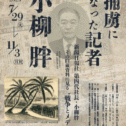
2025/08/24~2025/09/28
2025(令和7)年度│「愛と義の ひと・火坂雅志 追悼ミニ展示」
明和義人祭2025 記念トークの併催展示として、「愛と義のひと・火坂雅志 追悼ミニ展示」を開催します。
ここでは主に、8 月24 日(日) の記念トークに登壇された中川洋子さん(故 火坂雅志さん夫人) 所蔵の資料を展示しています。
没後10年のこの機会にぜひ、火坂雅志さんの仕事をしのんでいただきたいと思います。
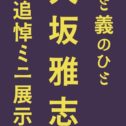
2024/04/02~2024/07/07
2024(令和6)年度|新潟日報紙掲載原画展
新潟日報の紙面では、これまでに新潟県内外の多くの作家が取り上げられてきました。新潟日報社は新潟県最大の新聞社として政治経済のみならず芸術文化の振興にも大きな力を注いできたのです。新潟日報社には、作家たちとの関わりの名中で集められた美術作品が多く所蔵されています。
これらの所蔵品から、本展では昭和30年代~50年代の新潟日報新年号を飾った作品や昭和40年代の『新潟日報アド・ジャーナル』(広告主向け情報誌)表紙に使われた作品を中心に紹介します。紙面を彩った作品群は新聞社ならではのコレクションです。この機会にぜひご高覧いただきたいと思います。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
監 修:横山秀樹氏(美術評論家、元新潟市新津美術館長)
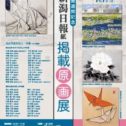
2024/07/30~2024/11/03
2024(令和6)年度|生誕160年記念 吉田東伍展—『大日本地名辞書』を中心に―
吉田東伍(1864~1918年)は越後安田(現阿賀野市)の地主・旗野家の三男に生まれました。学問を好む一族の中で育った東伍は、13歳で「分かりきったことしか教えてくれない」と嫌気がさして学校を退学すると、家業を手伝いながら、独学で知識を身に着けて、17歳で郷土誌『安田志料』を書き始めました。その後も小学校教員や志願兵、新聞記者の職に就きながら、現地調査を行い、1893(明治26)年刊行の『日韓古史断』で歴史家として認められました。
日清戦争従軍から戻ると、大叔父の小川心斎が残した未完の地誌『国邑志稿』を基礎資料として、全国の地名を集めた「大日本地名辞書』の編さんを始めます。東伍の構想は、単に地名を検索するための辞書でなく、その土地の自然的・文化的風土や特色を記した地誌、それも日本を統一した地誌を編さんするという、壮大なものでした。東伍は激励や支援を得ると、地名の歴史的な起源や変遷について研究、執筆を進めました。1907(明治40)年、13年かけて編さんした『大日本地名辞書』が完成。収録地名は約4万という偉業を独りで成し遂げました。
本展では、吉田東伍の生誕160年を記念して、阿賀野市立吉田東伍記念博物館などにご協力いただき、『大日本地名辞書』を中心に吉田東伍の業績を紹介します。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
展示協力:阿賀野市立吉田東伍記念博物館

2024/11/26~2025/03/09
2024(令和6)年度|没後30年記念 発酵学の父・坂口謹一郎と短歌
坂口謹一郎(高田町〔現上越市〕生まれ、1897~1994年)は、味噌や醤油、酒の醸造などに欠かせない発酵を化学的に解明し、日本の食生活の発展に貢献した、応用微生物学の世界的権威です。酒に関する著書や豊富な知識から「酒博士」と呼ばれ、親しまれました。
歌人としても評価されており、1975(昭和50)年、77歳の時には宮中歌会始の召人を務めました。坂口が作歌を始めたのは50歳前後のこと。研究生活の傍ら、自身の研究に向き合う姿勢や、酒を愛する歌、愛郷の歌などを詠みました。歌人・坂口謹一郎は、自らの歌を、自身が理想とする「喉に障りなく、水の如く飲める酒」のようでありたいと願っていました。
本展では没後30年を記念して、歌人としての坂口謹一郎を紹介します。
坂口 謹一郎(さかぐち・きんいちろう)新潟県高田町(現上越市)生まれ、1897(明治30)~1994(平成6)年
応用微生物学者、文化勲章受章者。
酒や味噌、醤油など麹菌を利用した発酵の過程を化学的に解明するなど、応用微生物学の世界的権威。高田中学(現高田高校)から東京の順天中学(現順天中学高校)を経て第一高等学校(現東京大学)に首席で入学。その後、東京帝国大学農学部で学び、卒業後は同校の教授になりました。お酒についての名著も多く、「酒博士」と呼ばれました。
日本初の微生物学研究の場「応用微生物研究所(現定量生命科学研究所)」を創設し、研究者の指導と育成にも力を尽くしました。
優れた歌人としても知られ、歌集『醗酵』があります。
1965(昭和40)年にフランスのレジオン・ドヌール勲章を、1967(昭和42)年に文化勲章を受章。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
展示協力:上越市、坂口記念館、新潟県醸造試験場、株式会社武蔵野酒造、株式会社杉田味噌醸造場、石本酒造株式会社、
発酵学の父 坂口謹一郎顕彰会

2023/04/12~2023/07/09
2023(令和5)年度|金子孝信 ~絵に託した熱き想い~
新潟市の蒲原神社に生まれた金子孝信は東京美術学校で学んだ後、26歳で戦死しました。志半ばで夢を断たれた孝信の想いを作品や資料から展観します。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
協 力:蒲原神社、新潟市潟東樋口記念美術館・新潟市潟東歴史民俗資料館
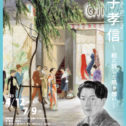
2023/08/01~2023/11/05
2023(令和5)年度|新井満回顧展―伝え続けた想い―
大ヒット曲「千の風になって」の翻訳、作曲で知られる新井満(1946~2021年、新潟市生まれ)。青年期に重病を患い生死を彷徨った体験から、生きる喜びを実感。以降、美しいものを発見し伝えることをライフワークとして生きたいと誓いました。
大学卒業後に入社した広告会社で環境映像制作に携わりながら、歌手や作詞作曲、執筆(のちに芥川賞受賞)など多様な分野で活躍しました。2008(平成20)年に『良寛さんの愛語』を発刊。この頃から新潟市「千の風のふるさと・新潟市」にも関わるようになりました。
様々なジャンルで活躍した新井満が生涯伝え続けた想いとは。関連資料とともに紹介します。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
監 修:竹石松次氏(BSNメディアホールディングス特別顧問)
展示協力:新井紀子氏、七飯町(北海道)、BSN新潟放送
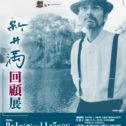
2023/11/28~2024/03/03
2023(令和5)年度|生誕140年記念 諸橋轍次と『大漢和辞典』ダイジェスト版
旧下田村(現三条市)出身の諸橋轍次は、2023年に生誕140年を迎えます。当館では過去に、歳月をかけて独力で大事業を成し遂げた4人の文化人を紹介する「越後人のねばり」展で諸橋轍次を紹介しましたが、紹介スペースには限りがありました。そこで生誕140年を記念して、改めて諸橋轍次を単独で取り上げ、世界最大の漢和辞典『大漢和辞典』を著した業績を中心に紹介します。
また、「併催ミニ展示」として、『和訳独逸辞典』の司馬凌海(佐渡市)、『大日本地名辞書』の吉田東伍(阿賀野市)、『新修漢和大字典』の小柳司氣太(新潟市)、『岩波中国語辞典』の倉石武四郎(上越市)、『会話作文英語表現辞典』のドナルド・キーン(柏崎市ゆかり)など、辞典編纂の業績がある新潟人も取り上げます。
主 催:にいがた文化の記憶館、新潟県、新潟日報社
共 催:新潟日報美術振興財団、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ
協力企業:田村紙商事株式会社
展示協力:諸橋轍次記念館、新潟県立図書館
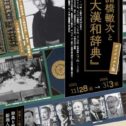
2022/04/09~2022/07/10
2022(令和4)年│生誕130年記念 直木賞作家 県人第1号 鷲尾雨工 ―人と作品―
歴史小説を多数発表し、新潟県人で直木賞作家第1号となった鷲尾雨工(本名浩、1892[明治25]~1951[昭和26]年)は、西蒲原郡黒鳥村(現新潟市西区)に生まれました。2022年に生誕130年を迎えます。
雨工の祖父と父は早くに亡くなり、生家は雨工が3歳の時に焼失したため、小千谷市にある母親の実家に移住しました。旧制小千谷中学校では常に成績上位で、卒業後は文学を志して早稲田大学英文学科に進学しました。卒業後、大学の同級生だった直木三十五らと出版業に乗り出しましたが、関東大震災で高額の負債を負って小千谷に帰郷しました。しかし作家への道を諦められずに再び上京し、職を転々としながら執筆活動を続けました。
再上京から11年、43歳の時に極貧の中で書き上げた『吉野朝太平記』で第2回直木賞を受賞。楠正儀(くすのき・まさのり)を中心に南北朝末期の乱世のありさまを描いた作品です。明確な歴史観に基づく歴史小説で評価を高めましたが、戦争や体調悪化のせいでその活躍は長く続きませんでした。
本展では生誕130年を記念し、鷲尾雨工の生涯と作品を紹介します。